一人親方が払う社会保険の金額はいくらになるのか気になる人もいるでしょう。
個人事業主である一人親方は原則、厚生年金保険や健康保険への加入義務はないものの、社会保険については国民年金と国民健康保険への加入が法律で義務付けられています。
今回は、一人親方が加入すべき社会保険の種類や各種社会保険料の計算方法について詳しく解説します。
建設業で働く一人親方で社会保険料について詳しく知りたい人はぜひ参考にしてください。
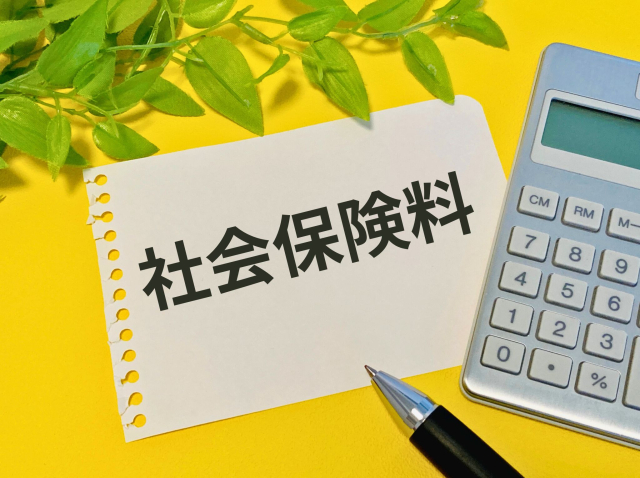
Contents
一人親方が加入すべき社会保険の種類と金額
社会保険とは、主に賃金を得て働く労働者が一定の条件を満たす場合に、加入が義務付けられる公的保険です。
社会保険には、厚生年金保険・健康保険・介護保険・雇用保険・労災保険が含まれ、そのうちの雇用保険・労災保険は「労働保険」と総称されます。
個人事業主である一人親方は原則、厚生年金保険や健康保険への加入義務はないものの、国民年金と国民健康保険への加入が義務付けられています。
ただし、一人親方が従業員を5人以上雇用している場合や法人化している場合は社会保険への加入が必要です。
一人親方が加入すべき国民年金と国民健康保険の金額についてそれぞれ解説します。
国民年金保険
国民年金は国民年金法に基づき、すべての日本国民が20歳から60歳までの間に加入が義務付けられている公的年金制度です。
国民年金に加入すると老後に一定の年金を受け取ることができます。
将来の老後資金を確保するためにも、国民年金への加入は個人事業主である一人親方にとって欠かせないでしょう。
令和7年度の国民年金保険料は1万7510円で、保険料は毎月一定で所得に応じた免除や減額申請ができます。
国民年金保険への加入手続きは、市区町村の年金課または最寄りの年金事務所で行い、基礎年金番号通知書や身分証明書の提出が必要です。
国民健康保険
国民健康保険は、個人事業主や無職の場合に加入する公的な医療保険制度で、一人親方の場合は居住する市区町村の国民健康保険への加入義務が国民健康保険法で定められています。
年間の保険料は自治体による差が大きく、一般的には前年の所得の7〜10%程度とされています。
保険料は各市区町村や収入の変動によって異なるため、正確な金額は、お住まいの市区町村の窓口やウェブサイトで必ず確認してください。
国民健康保険に加入すると、医療費の自己負担額3割が適用となり、医療費や薬代の軽減のほか、高額な医療費がかかった場合に自己負担の上限額が設けられます。
手続きは役所の国民健康保険課で行い、本人確認書類やマイナンバー、前年の所得証明書などが必要です。
介護保険
介護保険は、将来介護が必要になった際に介護サービス費用を一部負担してもらえる制度です。
特別な手続きは不要で40歳以上は自動的に加入となり、40~64歳は国民健康保険と介護保険料はセットで保険料が徴収され、65歳以上は市区町村から直接保険料が徴収されます。
保険料は所得に応じた金額で市区町村によって異なり、一般的に40〜64歳の場合で年間約2〜3万円といわれています。
40歳を迎える際は、介護保険料の支払いに備えて保険料の確認を行いましょう。
労災保険特別加入制度
建設業の一人親方は労働者に該当しないため、労災保険特別加入制度を利用して任意加入できます。
危険を伴う作業を行う一人親方にとって、労災保険特別加入制度は業務中の事故や通勤災害に対する療養費や休業補償を受けられる重要な保険です。
一人親方で特別加入を希望する場合は、労働局や労働保険団体を通じて申請書類を提出し、手続きを行います。
特別加入者の労災保険料は、給付基礎日額に365を乗じたもの(保険料算定基礎額)に各事業に定められた保険料率を乗じて計算されます。
年間保険料は、給付日額が3500円の場合で2万1709円、2万5000円の場合で15万5125円です。
一人親方は、自身の収入に応じて保険料を選択しましょう。
雇用保険
雇用保険は、失業中の労働者の生活の保障を目的とした保険で、解雇や自己都合退職などによって職を失った労働者が求職活動を行うことを条件に基本手当を受給できます。
失業保険や失業手当などの基本手当以外にも、育児休業等給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付などの給付があります。
一人親方は個人事業主のため、基本的に雇用保険への加入はできません。
ただし、一人親方としての事業とは別に労働者としての立場が生じると、雇用保険に加入できるケースがあります。
たとえば、ほかの会社や事業主に雇用される形で働く一人親方や自身の事業とは別にパートタイムやアルバイトとしてほかの会社で働く一人親方、法人の中で労働者として働く一人親方の場合などです。
各種社会保険料の算出方法

一人親方が加入できる各種社会保険の算出方法について解説します。
国民年金保険料
国民年金保険料額は毎年度異なり、平成16年の制度改正で決まった保険料額と物価や賃金の伸びに合わせて調整します。
国民年金保険料の計算方法は以下の通りです。
毎年度の国民年金保険料額=平成16年の制度改正で決められた保険料額×保険料改定率
保険料改定率=前年度保険料改定率×名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金変動率)
参考:日本年金機構「国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?」
国民健康保険料
国民健康保険は各自治体が管轄する制度で、保険料は前年の所得や加入者数、年齢によって変動します。
国民健康保険料は「医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳~64歳の方のみ)」の3つの要素から構成され、保険料の算出には所得割、均等割、平等割の3つの方式による複雑な計算が必要です。
| 所得割 |
|
| 均等割 |
|
| 平等割 |
|
保険料率は自治体ごとに差があり、上記の方式で算出した金額の合算額が1年間の保険料となります。
介護保険料
原則40歳以上は毎月介護保険料を支払う必要があり、保険料率は毎年見直されます。
個人事業主である40歳以上64歳未満の一人親方の場合、加入が義務付けられている国民健康保険料の一部として介護保険料が合算して徴収されるのが一般的です。
65歳以上の場合、保険料はお住まいの市区町村で必要な介護保険のサービス費用などから算出された基準額をもとに、所得に応じて決まります。
65歳以上の年金受給者の場合は、老齢年金からあらかじめ介護保険料が差し引かれた額が指定口座に入金され、年金未受給者の場合は納付書もしくは口座振替で支払いを行います。
定年退職後も保険料の支払いが必要で、年金受給者と年金未受給者で支払い方法が異なるため、年の途中で年金を受給するようになった場合は注意しましょう。
保険料の算定方法は加入している医療保険によって異なり、市区町村ごとに必要な介護保険サービスの量や65歳以上の人数によって基準額も異なるため、詳しくはお住まいの市区町村に確認してください。
労災保険料
労災保険料は、収入額に業種ごとに異なる労災保険料率をかけて算出します。
しかし、建設業では特に下請け業者の労働者の賃金を正確に把握することが難しい場合が多く、厚生労働省が定めた事業ごとの「労務費率」を請負金額に掛け合わせて賃金総額の推定額に労災保険料を掛けて保険料を計算します。
労災保険料の計算方法は、以下の通りです。
通常の労災保険料の計算方法=収入額×労災保険料率
建設業の労災保険料の計算方法=請負金額×労務費率×労災保険率
建設業の場合、「収入額」にあたる部分が「請負金額×労務費率」で、国に支払う労災保険料はどの加入団体でも金額は同一です。
しかし、加入団体によって入会金や組合費は異なり、更新や退会時、事故対応時、組合員証の再発行時など手数料が別途必要な場合があるため、事前に必ず確認しましょう。
令和7年度の労災保険料率と労務費率
建設事業における労務費率を事業別に表にまとめました。
| 労務費率 | 建設事業の種類 |
| 38% | 機械装置の組み立てまたは据付け事業の取り付けに関する事業 |
| 23% | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く) 既設建築物設備工事業 その他の建設事業 |
| 21% | 機械装置の組み立てまたは据付け事業に関するその他の事業 |
| 19% | 水力発電施設、ずい道等新設事業 道路新設事業 鉄道または軌道新設事業 |
| 17% | 舗装工事業 |
参考:厚生労働省「令和7年度の労災保険率等について」
令和7年度における建設業の一人親方の第2種特別加入保険料率は1000分の17となっています。
雇用保険料
自身の事業とは別にほかの会社や法人事業の中で労働者として働く一人親方の場合、雇用保険料が発生します。
雇用保険料の計算方法は、以下の通りです。
雇用保険料=毎月の給与額×保険料率
雇用保険料は、基本給以外にも残業代や通勤手当、住宅手当なども含む毎月の給与に雇用保険料率をかけて算出します。
保険料率は業種によって異なり、令和7年度の建設業の雇用保険料率は令和6年度と同率で、事業内容により1000分の6~1000分の34の範囲となっています。
一人親方の社会保険金額に関するよくある質問

一人親方の社会保険金額に関するよくある質問についてまとめました。
一人親方が払う社会保険料は経費として計上できますか?
一人親方の場合、社会保険料は本人に対する補償が目的とみなされます。
事業の継続に直接関係しないことから、経費としての計上はできません。
従業員であれば経費に計上できる保険でも事業者や専従者を対象とする場合は、経費として計上できないため、事業の経費とプライベートの出費が曖昧になりやすい個人事業主は、適切な経理管理が大切です。
確定申告では社会保険料控除として申告することで支払った保険料の全額を所得から控除できます。
納税額が不足すると税金の差額を徴収されるほか、ペナルティとして加算税が課される場合もあるため、注意してください。
一人親方労災保険特別加入制度には短期でも加入できますか?
労災保険への短期間での加入は、加入を認めている団体であれば可能です。
ただし、短期の加入を繰り返していると、年間で支払う保険料がかえって高くなるケースもあるため、注意しましょう。
また、短期加入者に発行する「労災保険加入証明書」の有効期限日は、年単位の3月31日とは違う日付になるため、短期加入する際は、期限切れに注意してください。
まとめ
一人親方が払う社会保険の金額は、国民年金保険で約1万8000円、国民健康保険は前年の所得の7〜10%程度です。
また、40歳以上に加入義務がある介護保険で約2〜3万円、労災保険特別加入制度では給付基礎日額に応じて約2~15万円となっています。
社会保険加入義務については明確な規定があり、加入すると労災事故によって被災した場合に一定の給付が受けられます。
労働者として雇われている一人親方は雇用保険料も発生するため、加入すべき社会保険の種類と金額の目安や計算方法を知っておきましょう。
