建退共は、将来の退職金が確実に受け取れる国の制度で、一人親方でも加入できます。
「建設業退職金共済制度」という名の通り、建設業界内であれば、転職時にも掛金を継続して積み立てられるため、老後資金が心配な一人親方でも安心して利用できる制度です。
今回は、建退共の概要や一人親方が建退共に加入するメリットやデメリット、掛金や年数によって受け取れる退職金の目安について解説します。
建退共制度について知りたい方や一人親方で建退共への加入を検討している方は本記事を参考にしてください。

Contents
建退共とは
建退共の正式名称は「建設業退職金共済制度」で、建設業従事者が建設業界から離職した際に退職金が受け取れる制度です。
「中小企業退職金共済法」に基づいて国が運営する制度として、建設業に関わる労働者の福祉と雇用の安定を築き、建設業の発展を目的としています。
各種手続きは各都道府県の建設業協会の支部で行い、事業主や任意組合を通じて実働日数に応じた掛金を支払います。
公共工事で問われやすい建退共の加入状況と辞退理由
国が運営する建退共制度は、元請けや発注した事業主によって加入状況を問われる場合があり、公共工事において加入状況を確認されるケースが多いようです。
建退共へ加入しない場合は「建退共以外の退職金制度に加入済」あるいは「加入の意思がない」ことを辞退理由として「建退共の辞退届」の提出を求められることがあります。
一人親方は建退共に加入できる?
一人親方でも建退共へ加入でき、現場が変わっても掛金を通算できる措置がとられています。
一人親方が建退共へ加入するためには、実働日数に応じた掛金の支払いと、事業主や元請会社から共済手帳に貼る証紙シールをもらうことが必要です。
建退共の加入対象となる方と対象外となる方について解説します。
建退共の加入対象となる方
建退共の加入対象となる方は、建設業で働くほぼすべての方です。
職種や給料、役職、国籍、建設業法の許可の有無や雇用形態を問わず、加入できます。
建退共の加入対象外となる方
建退共の加入対象外となる方は、以下の通りです。
- 事業主が法人の代表者
- 役員報酬を受けている方
- すでにほかの退職金共済制度に加入している方
- ほかの退職金制度に加入している方
ただし、ほかの退職金共済に加入している方が建退共に加入したい場合は、林業退職金共済や中小企業退職金共済などで納めた掛金を建退共制度に引き継いで加入することが可能です。
一人親方が建退共へ加入する方法
個人事業主である一人親方が建退共へ加入する方法について、それぞれ解説します。
一人親方同士で任意組合をつくる
一人親方が建退共へ加入するには、複数の個人が共同で事業を行うために団体を結成して、任意組合を作る方法があります。
既存の大工や左官組合などの組織を任意組合とすることも可能です。
任意組合をつくるには2人以上必要で、組合の運営や管理の負担が発生し、申請手続きの手間がかかる点に留意しましょう。
任意組合を作る流れは、次の通りです。
- 2人以上の一人親方同士で任意組合を結成
- 「組合の規約」「業務方法書」「任意組合認定申請書」を建退共の都道府県支部へ申請
- 建退共の都道府県支部からの「認定書のコピー」と「共済契約申込書」「共済手帳申込書」を提出
- 契約成立後に「共済契約者証」「退職金共済手帳」を受け取る
建退共に加入している組合から加入する
一人親方は、建退共に加入している既存の組合から加入でき、その際は個人での手続きは不要です。
各地域の組合によって加入条件や規約、組合費や掛金が異なるため、加入前によく確認しましょう。
建退共に加入している組合から加入する流れは、次の通りです。
- 建退共に対応している地域の建設業関連の組合や建退共制度を取り扱う団体を探す
- 加入申込み書類を組合へ提出
- 規約に沿って登録を行う
一人親方の場合、任意組合や事業主を通じて掛金納付するため、任意組合やほかの事業主から労働に応じて共済証紙シールをもらい、共済手帳へ貼ることで掛金を納付した証明となります。
建退共の加入費用と一人親方の退職金の目安金額

掛金の1日あたりの上限は320円で、初回加入金として約1500円、組合費が月額約500円かかります。
掛金を1日320円と仮定すると、建退共の掛金の目安は21日働いたとして月額6,720円かかり、初回加入金と組合費と合わせて最初の月は約8,700円となるでしょう。
建退共への加入期間が長いほど運用益が上乗せされた金額を受け取ることができ、加入期間が10年の場合の運用益は約9万円、20年の場合は約32万円となることが予想されます。
ただし、加入期間が5年以下の場合、利回りの恩恵は受けられない可能性が高いです。
最終的な退職金額は、加入期間や利回りの変動によって異なるものの、受け取れる退職金額の目安を一覧にまとめました。
| 掛金納付年数(加入月数) | 退職金額 | 掛金総額 | 運用益 |
| 1年(12ヶ月) | 約2万4,192円 | 8万640円 | 約ー6万円 |
| 2年(24ヶ月) | 約16万1,280円 | 16万1,280円 | 0円 |
| 5年(60ヶ月) | 約41万4,087円 | 40万3,200円 | 約1万円 |
| 10年(120ヶ月) | 約89万3,559円 | 約80万6,400円 | 約9万円 |
| 20年(240ヶ月) | 約193万3,479円 | 約161万2,800円 | 約32万円 |
| 25年(300ヶ月) | 約247万4,439円 | 約201万6,000円 | 約46万円 |
| 30年(360ヶ月) | 約303万8,919円 | 約241万9,200円 | 約62万円 |
| 35年(420ヶ月) | 約364万1,031円 | 約282万2,400円 | 約82万円 |
| 40年(480ヶ月) | 約426万8,007円 | 約322万5,600円 | 約104万円 |
| 45年(540ヶ月) | 約491万3,127円 | 約362万8,800円 | 約128万円 |
一人親方が建退共の退職金を受け取るための条件
一人親方が建退共制度で退職金を受け取るための条件は、次の通りです。
- 建設業を引退した場合
- ほかの業種に転職した場合
- 55歳以上になった場合
- 病気やケガで労働が困難な場合
- 本人が死亡した場合
退職金を受け取る条件を満たしていれば、前倒しで退職金を受け取ることもできます。
一人親方が建退共に加入するメリット
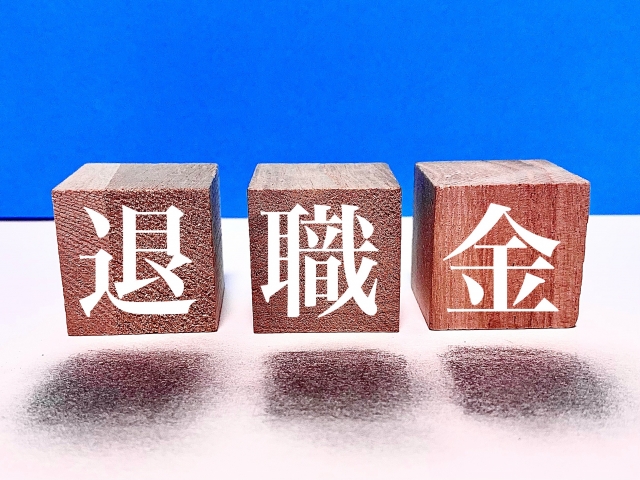
一人親方が建退共に加入するメリットについて解説します。
確実に退職金がもらえる
建退共に加入し、掛金を一定期間納付することで退職金を確実にもらえます。
一人親方にとって、少額から始められる建退共制度は退職金を積み立てやすく、老後が心配な方も安心です。
退職金の支給額は、勤務状況や掛金の納付期間に応じて増えるため、長年加入することで多くの退職金を受け取れます。
転職しても建築業界内なら加入し継続できる
一人親方は、転職して別の事業所に移るケースや一人親方として独立するケースなど、さまざまな働き方があるでしょう。
建退共は、転職しても建設業界で働く限り、継続して加入できるため、働き方が状況に応じて変わる一人親方も安心して退職金が受け取れる制度といえます。
ただし、建築業界以外に転職した場合は、加入を継続できないため、注意してください。
国による運用で長期的な資産形成が可能
建退共の利回りは、個人年金や金融機関の定期預金と比べて高く、長期的な資産形成に適した制度となっています。
個人での資産運用に比べて、リスクが少ないことから、安定して運用できる可能性が高いです。
また、国が運営する制度のため、共済手帳の初回交付時に50日分の掛金の補助があり、初期費用負担を軽減する措置が取られています。
一人親方が建退共に加入するデメリット
一人親方が建退共に加入するデメリットについて解説します。
受け取れる金額が少ないことがある
建退共の掛金の納付が短期間の場合、受け取れる退職金が掛金より少ない可能性があります。
また、掛金は上限が固定されているため、企業で働く労働者と比べて、個人事業主である一人親方が受け取れる退職金は少額となるでしょう。
このほか、事業主が正しく退職金掛金を支払っていないケースや正しい枚数分の証紙シールを貼っていないケースなどのトラブルもあるようです。
建退共の退職金が明らかに少ない場合は、シールの枚数を確認して建退共相談窓口や労働基準監督署に相談しましょう。
掛金はすべて自己負担
一人親方が建退共に加入する掛金はすべて自己負担です。
組合によっては、組合会費や加入時に入会金がかかるため、掛金以外にかかる費用をよく確認して加入を検討しましょう。
ただし、雇用されている場合は雇用主が掛金を全額負担するため、労働者に対する負担はありません。
建退共の掛金を経費にできない
建退共への加入は任意のため、個人的な積立となり、掛金は必要経費として認められません。
掛金の納入は、共済証紙シールを共済手帳に貼ることが証明となり、共済証紙の費用は一人親方の負担となり、所得控除の対象外です。
共済証紙シールは、事業主から労働日数に応じて交付され、共済手帳は加入後に交付されます。
ただし、退職金を受け取る際は、「退職所得控除」が受けられ、勤続年数が長いほど退職金の控除額は上がります。
加入期間が長いと税制上で優遇されるため、有利な税率で退職金を受け取ることができるでしょう。
まとめ
建退共は、建設業で働くすべての人が退職金を確実に受け取れる共済制度です。
一人親方は任意組合を作るか、建退共に加入している既存の組合から建退共へ加入できます。
一人親方が建退共に加入する場合の掛金は全額自己負担となり、短期間の加入では退職金が少額となる可能性があるため、注意しましょう。
建退共は長期積み立てで老後資金を確保しやすいことから、一人親方は自身の働き方に合わせて、加入を検討してください。
