建設現場や現場作業を担う一人親方にとって、仕事中のけがや事故は決して他人事ではありません。
しかし、仕事中にけがをした場合、保険証を使ってもよいのかと疑問に感じる一人親方もいるでしょう。
「仕事中にけがをしたら保険証を使えばよい」と思っている方は要注意です。
正しく手続きしないと、本来受けられる補償が受けられなかったり、受けるまでに時間と労力がかかってしまったりする可能性があります。
本記事では、一人親方が労災保険に加入している場合の保険証の使い方や、申請の流れ、受けられる補償内容について、解説します。
労災保険を受けるために保険証を使ってもよいのかと気になる一人親方は、ぜひ参考にしてください。
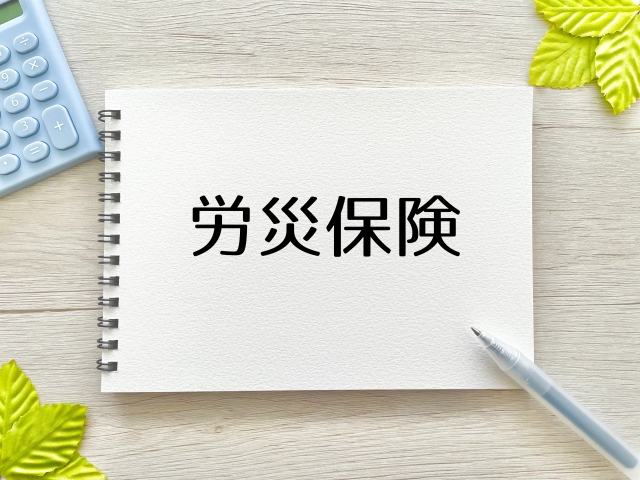
Contents
一人親方が労災保険を利用するときに保険証は使える?
一人親方が労災保険を利用する場合、健康保険証は使わない方がよいでしょう。
健康保険証で治療することは可能ですが、労災保険が適用できなくなるからです。
病院で健康保険証を使ってしまうと、通常のけがとして扱われ、労災保険の対象外になってしまいます。
その結果、本来なら補償される治療費を自分で負担したり、健康保険への返金や労災への申請という面倒な手続きが必要になったりします。
一人親方が業務中にけがをしたときは、病院に「仕事中のけがである」とはっきり伝え、健康保険証は出さずに労災手続きで対応することが大切です。
ただし、私生活中の病気やけがには、健康保険証を使用しましょう。
一人親方が労災保険を利用するときの流れ
一人親方が仕事中にけがをした場合、スムーズに労災保険の補償を受けるために正しい手順で対応することが重要です。
ここでは、労災保険を利用する際の基本的な流れを解説します。
病院で仕事中のけがであることを伝える
けがをしたらなるべく早く病院を受診し、仕事中のけがであると明確に伝えましょう。
病院では健康保険を使うのが一般的ですが、業務中のけがは労災保険の対象になるため、健康保険ではなく労災であることを最初に申告することが大切です。
特に労災指定病院であれば、必要な書類を提出するだけで窓口での支払いが不要になる場合もあります。
診察の受付で「労災です」としっかり説明することで、後のトラブルや面倒な切り替え手続きを避けられるでしょう。
加入している労災保険団体へ連絡する
医療機関での対応が終わったら、自分が加入している労災保険団体へ速やかに連絡しましょう。
労災保険の申請には、事故の詳細を記した「災害報告書」の提出が求められます。
この書類は団体ごとに書式が異なるため、ホームページなどから取り寄せる必要があります。
申請する際は、氏名や発生日、場所、けがの状況、受診先、作業内容などを正確に記入しましょう。
内容があいまいだったり、事実と異なったりすると労災が認められない恐れがあるため、当日の状況は詳細にメモしておくのがおすすめです。
事実に基づいた記録を残して正しい情報を提出することが、円滑な補償への第一歩になります。
労災申請書類を作成し提出する
次に、労災の補償を受けるために必要な申請書類を作成し、関係機関に提出しましょう。
書類は、加入している労災保険団体を通じて入手できます。
提出先は労働基準監督署ですが、団体が取りまとめて申請を代行するケースもあります。
申請時には団体の証明も必要となるため、まずは団体に報告し、必要書類を揃えてから提出するのがスムーズです。
補償の内容によって必要な書類が異なるため、団体の案内にしたがって用紙を選びましょう。
適切に申請すれば、医療費や休業補償などの給付を受けられます。
労災なのに一人親方が保険証を利用してしまったときの対応方法
業務中のけがなのに、うっかり健康保険証を使って治療を受けてしまうこともあるでしょう。
このような場合は、まず治療を受けた医療機関に連絡し、労災への切り替えが可能かどうかを確認しましょう。
切り替えができるか否かで対応が変わりますが、どちらにしても早めの行動が大切です。
ここでは、労災保険に切り替えられる場合と切り替えられない場合の対処法について解説します。
切り替えられる場合
医療機関が労災への切り替えを認めた場合は、速やかに必要な書類を用意しましょう。
この場合に使うのが「療養補償たる療養の給付請求書(様式5号)」です。
必要事項を記入して関係機関に提出すれば、治療費は労災保険でカバーされます。
切り替え手続きが完了した後は、原則として労災指定の医療機関で治療を継続することが望ましいです。
そうすることで、記録や請求処理がスムーズに進みます。
病院を変える必要が出る場合もあるため、指示に従いながら正しい対応を心がけましょう。
切り替えられない場合
労災への切り替えが認められない場合も、補償を受ける方法はあります。
このときは、「療養補償たる療養の費用請求書(様式7号)」を使い、受診した病院に記入を依頼しましょう。
その後、自分で労働基準監督署に提出する手続きが必要です。
医療費の全額を一時的に自己負担し、健康保険で処理された分は返金対応となります。
最終的には労災保険から給付があるため、実質的な負担はありません。
ただし、返金や給付までには時間がかかるため、大きな出費を一時的に負担することになります。
一人親方が労災保険を利用するときの注意点

一人親方が労災保険を利用するときに注意すべき点は、2つあります。
どのような点に注意すべきか、解説します。
労災指定病院を受診する
労災保険を使って治療を受けるなら、まず労災指定の医療機関を選ぶようにしましょう。
労災指定病院では窓口で治療費を払う必要がなく、費用は労災保険から直接支払われます。
一方、一般の病院を利用した場合は、いったん全額を立て替えて支払い、後日、自分で労働基準監督署に申請して医療費を返してもらう流れになります。
手続きの手間や経済的な負担を減らすためにも、できる限り最初から労災指定病院を受診するのが賢明です。
近くの指定病院を事前に調べておくと、緊急時にも安心です。
元請けの労災保険は使えない
元請け会社の労災保険が使えると思っている一人親方の方もいるかもしれませんが、実際には適用されません。
労災保険は「雇用されている労働者」に向けた制度であり、請負契約で働く一人親方は対象外です。
そのため、自分で特別加入制度を利用して労災保険に加入しておかなければ、仕事中にけがをしても何の補償も受けられません。
自分の身を守るためにも、元請けに頼らず一人親方としての加入手続きを行っておくことが重要です。
一人親方が労災保険に加入するなら、一人親方団体労災センターをご検討ください。
一人親方団体労災センターは、労災保険料と月々わずか500円の組合費で、全国どこでもスムーズに加入可能です。
また、面倒な手続きは不要で、労災事故の申請書類作成なども無料でサポートいたします。
一人親方は、自分の身は自分で守る必要があるため、ぜひ労災保険の加入をご検討ください。
一人親方が労災保険を使えるケース

一人親方でも、特別加入していれば業務中や通勤中のけがに対して労災保険を使えます。
ただし、労災の補償が受けられるのは、仕事と認められる行為や合理的な通勤中の事故に限られるのです。
建設業に従事している場合、以下のような場面で労災が適用されます。
- 請負契約に基づき実際に作業を行っているとき
- 工事現場で作業しているときや、その準備や片づけをしているとき
- 自宅の作業場で、請負契約に関連する仕事をしているとき
- 工事に必要な資材や機械を運んでいるとき
- 台風や火災など、予期せぬトラブルで急きょ出勤したとき
- 自宅と現場の間を、無駄な寄り道なく往復している通勤途中の事故
一方で、仕事の帰りに飲食店へ寄った後のけがなど、就業と関係ない移動中の事故は補償の対象外です。
仕事中または正しい通勤中であることが、労災保険を受けるための条件となります。
参照:厚生労働省「特別加入制度のしおり<一人親方その他の自営業者用>」
一人親方が労災保険で受けられる補償
一人親方が労災保険に加入していると、業務中や通勤中のけが・病気・死亡などに対して、さまざまな補償を受けられます。
補償の内容は、療養や休業、障害、死亡といった状況に応じて細かく分かれており、それぞれに支給条件と金額の目安があります。
一人親方が労災保険で受けられる補償は以下のとおりです。
| 給付の種類 | 支給条件 | 給付内容 | 特別支給金 |
| 療養補償給付 | 業務・通勤でケガや病気になった場合 | 無料で治療を受けられるか、費用が支給される | なし |
| 休業補償給付 | 4日以上労働できない場合 | 1日につき給付基礎日額の60%が支給される | 別途20%を支給(合計80%) |
| 障害補償給付 | 障害が残った場合 | 障害の等級に応じて年金または一時金が支給される | 一時金支給(1級=342万円など) |
| 傷病補償年金 | 傷病が1年6ヶ月以上治らず重度障害が残る場合 | 年金が支給される | 一時金(1級=114万円など) |
| 遺族補償給付 | 業務等で死亡した場合 | 遺族の人数に応じて年金支給される | 一律300万円(年金に加算) |
| 遺族一時金 | 遺族年金の対象者がいないなど | 遺族の人数に応じて一時金が支給される | 一律300万円(年金と併用不可) |
| 葬祭料 | 労災による死亡時の葬儀費用 | 一定の金額が支給される | なし |
| 介護補償給付 | 重度障害で介護が必要な場合 | 介護費用が支給される | なし |
一人親方として働くなら、どのような場面でどんな補償が受けられるかを確認しておきましょう。
参照:厚生労働省「特別加入制度のしおり<一人親方その他の自営業者用>」
まとめ
一人親方として働くなら、労災保険への特別加入は自分自身を守る大切な備えです。
業務中や通勤途中のけが・病気に対して補償を受けるには、加入だけでなく、正しい使い方を知っておくことが欠かせません。
特に注意すべきなのは、労災保険を利用する場合に健康保険証は使えないという点です。
健康保険証を使ってしまうと労災扱いにならず、本来受けられる補償が受けられなくなる可能性があります。
事故が起きたときは、病院に「仕事中のけが」と明確に伝え、保険証は提示せず、労災の手続きで対応しましょう。
労災保険の仕組みを理解し、申請方法や補償内容を把握しておくことで、万が一のときにも落ち着いて行動でき、自分の生活を守ることにつながります。
