一人親方で税金を払ってないとどうなるのか気になる人もいるでしょう。
個人事業主である一人親方は毎年確定申告を行い、正しく納税する必要があります。
今回は、一人親方で税金を払ってないとどうなるのか、具体的なペナルティや確定申告の方法について解説します。
支払うべき税金の種類や、無申告が発覚するケースを知りたい人も参考にしてください。
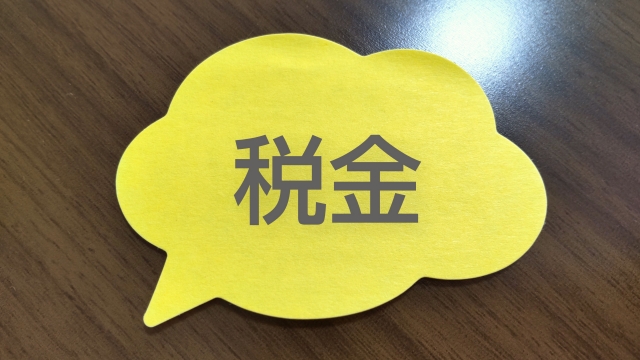
Contents
一人親方が税金を払ってないとどうなる?
一人親方で税金を払ってないと刑事罰の対象となり、仕事面と生活面に影響を及ぼす可能性があります。
個人事業主に該当する一人親方は自ら確定申告を行い、所得税額を算出する必要があり、申告期限を過ぎるとペナルティが課されてしまいます。
スケジュールに余裕を持って必ず指定された期日を守りましょう。
例外として、一人親方でも確定申告が不要なケースは、所得税がゼロになる場合です。
赤字の場合・収入から必要経費を差し引いた所得額が48万円以下の場合などが挙げられます。
一人親方が支払う税金の種類
一人親方が支払う税金には、所得税や消費税といった「国税」、個人事業税・住民税などの「地方税」があります。
| 税金の種類 | 概要 | 支払う時期 |
| 所得税 | 1年間の所得に対して課税される国税 | 毎年2月中旬~3月中旬(確定申告) |
| 消費税 | 商品やサービスの提供に対して課される国税
|
課税期間の翌年3月31日まで |
| 個人事業税 | 個人事業主が都道府県に対して納める地方税
|
原則8月末日と11月末日の2回 |
| 住民税 | 住んでいる自治体に納める地方税 | 毎年6月頃に納付書送付 |
税金の支払いは義務のため、各種税金の納付期限や納付要件を理解して納税しましょう。
税金を払っていない場合のペナルティ

税金を正しく払っていないと、税務調査の対象となる場合があります。
税金を払ってない場合に課されるペナルティについて詳しくみていきましょう。
加算税が課される
加算税とは、確定申告を期限内に申告や納付しなかった場合に税務署から課される税金です。
加算税は、申告期限を過ぎてから申告した場合でも課税され、無申告の期間が長いほど金銭的負担が増加してしまいます。
また、期限内に確定申告をしても虚偽の申告をしていた場合は、重加算税が加算される場合があります。
重加算税とは、隠蔽や虚偽の申告をした場合に加算税に代えて課税される税金です。
無申告によるペナルティは税務調査前に確定申告をする場合と、税務調査後に確定申告をする場合で加算税率が異なります。
加算税の種類やペナルティの概要について表にまとめました。
| 加算税の種類 | ペナルティの概要 | 加算税率 |
| 期限後申告 | 税務調査前に確定申告した場合
|
原則10%(更正等予知前5%) |
| 無申告加算税 | 税務調査後に確定申告した場合 | 50万円以下:原則15%(調査通知後10%) 50万円~300万円以下:原則20%(調査通知後15%) 300万円~:原則30%(調査通知後25%) 調査通知前:5% |
| 過少申告加算税 | 所得を過少申告した場合 | 50万円以下:原則10%(調査通知後5%) 50万円以上:原則15%(調査通知後10%) 調査通知前:不適用 |
税務調査を受ける前に確定申告を行うことで加算税率が減額される場合もあるため、早めに申告しましょう。
延滞税が課される
延滞税は、納付期限後に遅れて支払った税金に課せられる税金です。
法定期限の翌日から納税が完了するまで日割りで加算されるため、無申告の状態が長いほど高額になります。
延滞税率は年度によって異なりますが、令和3年1月1日以後は「延滞税特例基準割合+1%」のどちらか低い割合となります。
延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合です。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの税率を以下の表にまとめました。
| 期間 | 国税 | 期間 | 地方税 |
| 納期限翌日から2か月まで | 年2.4% | 納期限翌日から1か月まで | 年2.4% |
| 納期限翌日から2か月以降 | 年8.7% | 納期限翌日から1か月以降 | 年8.7% |
国税と地方税では、延滞税の対象期間が異なるため、注意が必要です。
確定申告の法定期限は毎年3月15日、住民税の納期は一括払いの場合は6月末まで、分割払いの場合は6月末、8月末、10月末、翌年1月末までとなっています。
納期限内に必ず納付し、もし確定申告が遅れそうな場合は早めに税務署に相談しましょう。
収入証明が必要なサービスが受けられない
一人親方が確定申告をしていないと収入を証明できないため、住宅ローンや自動車ローンの申請や賃貸の契約、補助金の申請などの審査に通りにくくなります。
収入証明書は税務署が発行するため、信頼性が高く、取引先や金融機関からの信頼を得ることができます。
収入証明がないと金融機関からの信用が低下するほか、取引先との契約を結べない可能性があります。
特に、一人親方は毎月の収入状況が不安定なため、給付金や補助金を受け取れないデメリットは大きいでしょう。
建設業の許可が受けられない
建設業法第3条に基づき、原則、建設工事を請け負うためには公共・民間に関わらず建設業許可が必要です。
建設業許可を得るためには、財務状況や収入を証明する書類が必須のため、確定申告を行わないと収入の証明ができず、許可を得られません。
ただし、以下の軽微な建設工事を請け負う一人親方の場合は、建設業許可は不要です。
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- 1500万円未満の建築一式工事
- 上記以外の500万円未満の専門工事
大きな仕事を考えている一人親方の場合は、建設業許可を申請し、新規案件の受注や業務の幅を広げるとよいでしょう。
一人親方の無申告が発覚するケース

一人親方が確定申告を怠ると税務署に発覚する可能性があります。
無申告が発覚する4つのケースについてみていきましょう。
取引先に税務調査が入った場合
税務署は取引先の帳簿を詳細に調べるため、取引先が受ける税務調査の過程で一人親方の無申告が発覚することがあります。
取引先から一人親方宛に発注した工事の契約書や材料の納品書、入出金の履歴などを申告内容と照合する可能性があります。
工事の発注元や材料の仕入れ先などの取引先と一人親方の申告内容が一致しないことが判明した場合、無申告が明らかになるでしょう。
第三者からの情報提供があった場合
知人や関係者などの第三者からの情報提供によって無申告が発覚するケースがあります。
税務署は匿名の通報や密告により調査を行う場合があり、従業員や取引先の担当者など関係者からの情報提供によって無申告が発覚するケースは少なくないようです。
予期せぬ所から税務署へ情報が伝わり、無申告が明らかになる場合もあるため、日々の記録を漏れなく申告しましょう。
車や不動産を購入した場合
一般的に、高額な買い物をする際は購入資金の出所や収入状況の証明が求められるため、車や不動産の購入時は注意が必要です。
金融機関や販売業者が税務署に資産移動の情報を提供することで、無申告が明らかになる可能性があります。
車や家の購入など大きな買い物の際は、資金の出所について税務署から確認されることを想定して、日頃から正確な申告を行うことが大切です。
取引先が提出する支払調書に記載があった場合
取引先が支払調書を提出していると報酬の支払い先として一人親方の名前と支払い額を税務署に提出しているため、一人親方の無申告が明らかになる可能性があります。
一人親方が取引先と業務委託契約を結んで仕事を請け負う際、取引先は成果物の提出を条件に一人親方へ報酬を支払います。
企業や個人事業主は報酬を支払った場合、支払調書で支払い先の氏名や住所、報酬の総額などを報告する義務があり、税務署へ1月末までに支払調書の提出が必要です。
取引先の支払調書に一人親方の名前があるのに、確定申告がされていないと税務調査の対象となるでしょう。
正しい税金の払い方(申告方法)4ステップ
一人親方は毎年確定申告を行い、1年間の所得額を計算したうえで、所得に応じて課せられる所得税を納税しなければなりません。
正しい税金の払い方(申告方法)について解説します。
必要書類を用意する
まずは確定申告に必要な売上・経費・控除など、お金に関する書類を準備しましょう。
- 売上に関する書類:請求書、支払調書、売上帳簿など
- 経費に関する書類:材料費や交通費などの領収書やレシートなど
- 控除に関する書類:社会保険料の納付書、医療費通知書など
必要書類は、1年かけてその都度保管しておき、事業におけるお金の動きはすべて記帳します。
確定申告書を作成する
次に、用意した書類や帳簿を参考に確定申告書を作成します。
確定申告書は、手書きまたは確定申告ソフト、確定申告書等作成コーナーを活用して作成できます。
書類の整理や帳簿への記帳は時間がかかるため、手間を減らしたい方や不安な方は確定申告書の作成を税理士に依頼することも1つの方法です。
必要書類の整理や記帳をコツコツとやっておくことでスムーズに確定申告書を作成できるでしょう。
確定申告書を提出する
確定申告書の作成後は、申告期限内に提出をします。
確定申告書の提出期間は、年によって数日変わるものの毎年2月16日から3月15日付近です。
期限を過ぎるとペナルティを課される可能性があるため、余裕を持って提出しましょう。
提出方法は、税務署で直接提出するか、郵送またはオンライン上のe-Taxです。
e-Taxは、国税庁が提供するオンラインの申告システムです。
マイナンバーカードやICカードリーダーがあれば、スマホからもアクセスすることができます。
「ID・パスワード方式」の場合は税務署で事前に発行する必要があるものの、画面の指示に従って収入金額や必要経費を入力するだけで税額が自動計算されるため、手間をかけずに申告できます。
所得税を納付する
確定申告書の提出後は、所得税をクレジットカード、口座引き落とし、コンビニ、税務署や金融機関から納付します。
確定申告は所得税の納付であり、納税が遅れると延滞税が発生するため、期日を守りましょう。
源泉徴収で税金を払い過ぎている場合は、確定申告を行うことで数か月後に還付を受けられます。
まとめ
税金を払ってない一人親方は、取引先の支払調書や車や不動産の購入時、第三者からの情報提供などにより発覚する可能性があります。
一人親方で税金を払ってないと補助金や住宅・自動車ローンの申請、賃貸の契約などの審査に通りにくく、建設業の許可が受けられないでしょう。
正確に確定申告を行わない場合や申告期限を過ぎた場合は加算税や延滞税が発生するため、スケジュールに余裕を持って正しく納税することが大切です。
