仕事の波が激しく収入が安定しにくい一人親方にとって、事業資金の確保は大きな課題です。
そんな中、給付金を活用することで経営の不安を軽減できる可能性があります。
しかし、制度の種類や申請条件が複雑で、「どの給付金が申請できるのか分からない」と感じる方もいるでしょう。
本記事では、一人親方でも申請できる給付金6選と、その探し方、申請時の注意点までを解説します。
申請できる給付金が知りたい一人親方は、ぜひ参考にしてください。

一人親方が申請できる給付金6選
一人親方として事業を続けていくうえで資金面の不安を感じたとき、公的な給付金や補助金は心強い味方となります。
ここでは、一人親方でも申請できる給付金などを6つご紹介します。
【事業を切り替えたい方なら】事業再構築補助金
事業再構築補助金は、ポストコロナ時代を見据えて新たな分野への挑戦や事業の再編に取り組む中小企業・個人事業主を後押しする制度です。
対象や補助金額は、以下のとおりです。
| 事業類型 | 対象 | 補助上限額 | 補助率 |
| 成長分野進出枠(通常類型) |
|
【従業員数20人以下】 1500万円 (※2000万円) |
• 1/2(※2/3) |
| 成長分野進出枠(GX進出類型) |
|
【従業員数20人以下】 3000万円 (※4000万円) |
• 1/2(※2/3) |
| コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) |
|
【従業員数5人以下】 500万円 | • 3/4(一部2/3)
|
※短期に大規模な賃上げを行う場合
この補助金は、事業の転換や拡大を真剣に考えている一人親方にとって、大きな資金的支援となるでしょう。
参照:経済産業省 中小企業庁「事業再構築補助金 第13回公募の概要」
【販路を広げたい・集客を増やしたい方なら】小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率の向上を目指す小規模事業者を支援するための制度です。
新規顧客向けの商品開発やホームページの作成など、売上向上につながる取り組みが対象です。
業務目的が限定されない車やパソコンなどは対象外であるように、使用目的が明確である必要があります。
補助の上限は通常50万円で補助率は2/3ですが、インボイス対応や賃上げなど特定の条件を満たす場合は最大200万円が上乗せされます。
対象経費は、機械装置費、広告費、展示会出展費、Web関連費、新商品開発費などです。
個人事業主が申請する場合、経営計画書や商工会議所が発行する事業支援計画書、確定申告書類などが必要で「GビズIDプライム」の取得も必須です。
申請準備にはある程度の時間がかかる点に留意しましょう。
参照:小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第18回公募 公募要領」
【事業を引き継ぎたい・譲りたい方なら】事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金は、中小企業や個人事業主が行う事業承継やM&Aを支援する制度で、後継者への引き継ぎや他事業者との統合・再編の際にかかる経費を一部補助してくれるものです。
制度は4つの枠に分かれており、目的に応じて適切な枠を選ぶ必要があります。
それぞれの、対象や対象経費は以下のとおりです。
| 事業承継促進枠 | 専門家活用枠 | PMI推進枠 | 廃業・再チャレンジ枠 | |
| 対象 | 5年以内に親族内承継または従業員承継を予定している事業者 | 補助事業期間に経営資源を譲り渡す、または譲り受ける事業者 | M&Aにともない経営資源を譲り受ける予定の中小企業等に係るPMIの取り組みを行う 事業者 | 事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業等を行う事業者 |
| 対象経費 | 設備費 産業財産権等関連経費 謝金 旅費 外注費 委託費 など |
謝金 旅費 外注費 委託費 システム利用料 保険料 |
設備費 外注費 委託費等 |
廃業支援費 在庫廃棄費 解体費 原状回復費 リースの解約費 移転・移設費用(併用申請の場合のみ) |
申請を検討する際には、自身の事業状況と制度の対象枠を照らし合わせ、補助対象の経費や必要な要件をしっかり確認しましょう。
詳細な金額や補助率は、ホームページをご確認ください。
参照:中小企業庁「令和6年度補正予算「事業承継・M&A補助金」で中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用等を支援します!」
【IT化やDXを進めたい方なら】IT導入補助金

IT導入補助金は、業務効率化やデジタル化を進めたい中小企業・個人事業主を対象とした制度です。
会計ソフトや在庫管理システム、クラウド型の請求書管理ツールなど、業務改善につながるITツールの導入費用が補助されます。
対象ツールは、補助金サイトに登録されたものから選ぶ必要があります。
申請枠の種類と内容は以下のとおりです。
| 申請枠 | 内容 |
| 通常枠 | ソフトウェア・システムの導入支援(在庫管理・決済システムなど) |
| インボイス枠(インボイス対応類型) | インボイス制度に対応する会計・受発注ソフトやハードウェアの導入支援 |
| インボイス枠(電子取引類型) | 商流単位で電子取引システムを導入する企業への支援 |
| セキュリティ対策推進枠 | サイバーリスクに対応するためのセキュリティツール導入支援 |
| 複数社連携IT導入枠 | 地域の事業者同士で連携し、DXを推進する取り組みを支援 |
通常枠の補助率は1/2で、補助金額はITツールの業務プロセス数によって5万円〜450万円です。
IT導入補助金は、日々の業務を効率化し利益率向上を図りたい一人親方にとって非常に有用な制度といえるでしょう。
参照:IT導入補助金2025
【従業員のスキルアップを目指したい方なら】人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、従業員の研修や技能向上に取り組む事業主を対象とした制度で、訓練費用や賃金の一部が支給されます。
現在従業員がいない一人親方は対象外ですが、今後人を雇用する予定がある方にとっては、将来的に活用できる可能性があります。
支援対象となるコースは、以下のとおりです。
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
- 障害者職業能力開発コース
申請は、訓練開始の6ヶ月前~1ヶ月前までに計画書を労働局へ提出します。
その後、訓練を実施し、終了後2ヶ月以内に支給申請を行います。
将来の人材育成に備え、制度内容を事前に把握しておくと安心です。
【地域密着で支援を受けたい方なら】地方自治体独自の助成金・補助金
国の制度に加え、地方自治体が独自に実施している助成金や補助金もあります。
一人親方でも、個人事業主向けの枠で対象になることがありますが、内容や条件は自治体によって異なります。
情報収集には、地域や目的別に検索できる「補助金ポータル」が便利です。
また、自治体の窓口で直接相談するのも有効です。
自分に合った制度を見つけるため、複数の方法で情報を確認しましょう。
一人親方が利用できる給付金を探す方法

給付金などは種類も多く、自分に該当するかどうかの判断が難しいと感じる一人親方も多いでしょう。
しかし、正しい情報にアクセスできれば、事業の支えとなる制度を見つけられます。
ここでは、給付金を見つけるための2つの方法を解説します。
取引先に確認する
まず試したいのが、取引先への確認です。
特に、経験豊富な元請業者や先輩の職人は、給付金や補助金を活用した事例を知っている可能性があります。
実体験をもとに、具体的なアドバイスをもらえることもあるでしょう。
有益な情報を得るには、取引先や同業者との関係を良好に保つことも重要です。
信頼できるネットワークは、制度活用のきっかけになります。
自治体の相談窓口に問い合わせる
もう1つの方法は、自治体の相談窓口に問い合わせることです。
給付金の多くは地方自治体でも実施されており、内容や条件は地域によって異なります。
窓口では、利用できる制度や申請方法について詳しく説明してもらえます。
相談は電話でも可能です。
あわせて自治体のホームページや広報紙も確認するとよいでしょう。
一人親方が給付金を申請するときの注意点
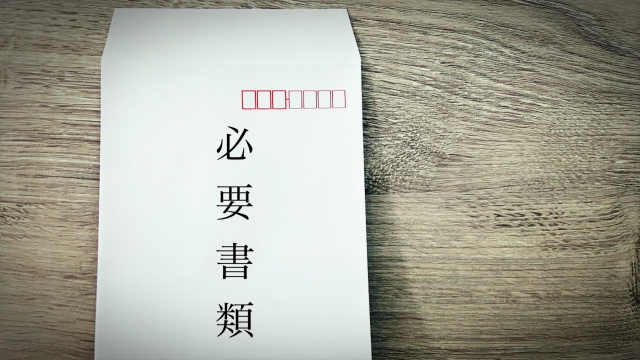
給付金や補助金を活用するには、事前に制度を理解し、申請の手順や注意点を把握しておくことが重要です。
ここでは、申請にあたって気をつけたい4つのポイントを解説します。
申請期限内に提出する
多くの給付金には、あらかじめ申請期間が定められています。
この期間を過ぎてしまうと、たとえ申請条件をすべて満たしていても受け付けてもらえません。
特に人気のある制度では、申請期間が短くなっているケースもあります。
こまめに公募情報をチェックし、余裕を持って準備・提出するようにしましょう。
提出書類に不備がないようにする
申請時には複数の書類を提出する必要があり、その内容の正確さが求められます。
書類の記載ミス、漏れ、添付書類の不足があると、申請が却下されたり審査に遅れが出たりする原因になります。
一人親方は自分自身で全てを準備することが多いため、事前に必要な書類を把握し、内容を丁寧に確認することが重要です。
受給まで時間がかかる
補助金制度の多くは、事業を実施したあとに費用の一部が支給される後払い方式を採用しています。
そのため、事業を実施するための費用を一時的に自分で用意しなければなりません。
申請から入金まで数ヶ月から1年近くかかるケースもあります。
こうした前提を踏まえて、無理のない資金計画を立てておくことが大切です。
受給できないケースもあることを理解しておく
条件を満たしていても、審査の結果によっては給付されないケースがあります。
多くの制度では、申請内容の妥当性や必要性が評価の対象となり、競争率が高い場合もあります。
また、記載ミスや誤解を招く内容は不正と見なされる可能性があるため、制度の目的を理解して正確な申請をすることが重要です。
まとめ
一人親方として事業を続けていくうえで、給付金は経済的な支えになる重要な制度です。
本記事で解説した給付金は、いずれも要件を満たせば一人親方でも申請できる可能性があります。
給付金を活用するためには、制度の内容を正しく理解し、申請の流れや注意点を把握しておくことが大切です。
ただし、申請には期限や条件があり、準備不足では受給できないこともあるため注意が必要です。
取引先や自治体から情報を得ながら自分に合った制度を見つけ、事業の安定や成長につなげていきましょう。
