労災で負傷後、なかなか痛みが取れないときは早期回復のために、整骨院でのリハビリ治療が必要となることは少なくありません。
そこで、整骨院での施術は労災申請できるのか気になる一人親方もいるでしょう。
本記事では、整骨院や接骨院で労災申請できる条件や労災申請する方法について解説します。
必要な書類を知りたい人や労災保険が認められない事例について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

Contents
整骨院や接骨院でも労災保険を使って受診できる?
仕事や通勤中にケガをした場合、病院で診断を受けることで整骨院や接骨院でも労災申請が可能です。
労災保険が適用されると、整骨院や整形外科での負担金がなくなり、休業補償を受けられるなどのメリットがあります。
労災保険での受診は、業務中や通勤中のケガの治療だけでなく、手術後のリハビリも対象です。
ただし、整骨院での施術を労災請求できるのは「整骨院への通院が必要と医師が判断した場合」に限られます。
整骨院で施術を行う柔道整復師は医師ではないため診断書を作成できません。
医師の診断なしに整骨院で施術を受けても労災請求はできないため注意が必要です。
整骨院や接骨院で労災申請できる条件
整骨院や接骨院で労災申請できる条件について、それぞれ解説します。
業務災害または通勤災害に該当する場合
労災保険は業務中に起きた「業務災害」だけでなく、出張時や通勤中の「通勤災害」など、職場の環境や管理不足が原因で起きた災害に対して適用されます。
ただし、業務中であっても私的な行為で災害が発生した場合、労災保険は原則適用されません。
労災保険は日雇い労働者やパート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、すべての労働者が対象です。
建設業で働く一人親方は労災保険特別加入制度を利用することで補償を受けられます。
医師から整骨院での施術が必要と診断された場合
整骨院や接骨院で労災申請できる条件は、医師から整骨院での施術が必要と診断された場合に限られます。
事故やケガで負傷した場合は、早めに病院を受診して医師から診断を受け、速やかに労災認定を受けましょう。
負傷してから受診まで時間が空いてしまうと、仕事との因果関係が認められない場合があります。
また、施術期間が長期にわたる場合、整骨院のみの受診だけでは労災保険とは認められません。
請求書とともに定期的に医師の診断書の提出が必要です。
必要書類を提出して労災申請手続きをした場合
労災申請するためには、必要書類を提出して労災であることを証明し、適切な補償を受けるための手続きが必要です。
労災申請手続きを行うことで、治療費は全額労働基準監督署から支払われるため、自己負担なしで施術を受けることができます。
労災保険は自由診療扱いとなり、健康保険と違い、窓口での一部負担金は発生しません。
労災保険で整骨院を受療する流れと申請方法
労災保険で整骨院を受療する流れは以下の通りです。
- 事故発生後すぐに病院を受診して診断を受ける
- 医師から整骨院での治療が必要と診断されたら診断書や紹介状を受け取る
- 医師から受け取った書類を持参して労災対応の整骨院へ行く
- 施術ごとに発行される施術証明書は必ず保管しておく
施術証明書は労災保険の申請に必要なため、治療の経過が分かるように定期的に書類を整理しましょう。
労災保険特別加入団体を通じて労災事故の詳細報告を行い、労災申請書類を作成して提出することで手続きは完了します。
医師の指示をもとに、リハビリのため整骨院への受診や病院の転院、休業申請、障害補償申請などが必要な場合、その都度特別加入団体へ連絡して必要書類を作成します。
整骨院で労災申請する際に必要な書類
整骨院で労災申請する際に必要な書類は、以下の通りです。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 事故証明書 | 事故の発生を証明するための書類 |
| 診断書 | 医師が治療の必要性や治療期間などを記載する書類 |
| 費用請求書 | 柔道整復師が傷病の経過状況を記入する書類 |
費用請求書は厚生労働省のHPからダウンロードでき、基本的に1ヶ月に1枚を提出します。
柔道整復師が記入する書類には右上に「柔」マークがあり、通勤災害用と労働災害用で様式が異なるため注意してください。
| 種別 | 書類名 | 様式 |
|---|---|---|
| 業務災害 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(柔整) | 第7号(4) |
| 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう) | 第7号(3) | |
| 通勤災害 | 療養給付たる療養の費用請求書(柔整)通勤災害用 | 第16号の5(3) |
| 療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)通勤災害用 | 第16号の5(4) |
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
労災保険柔道整復師施術料金算定基準
| 算定項目 | 施術料金 |
|---|---|
| 初検料 | 2,575円 |
| 初検時相談支援料 | 150円 |
| 再検料 | 490円 |
| 往療料 | 2,760円 |
| 指導管理料 | 680円 |
| 休業証明書 | 2,000円 |
| 運動療法料 | 380円 |
ただし、整骨院で行われる手技療法や物理療法などすべての治療が労災保険の適用範囲内とは限りません。
一部の代替医療や特定の治療機器を使用した治療は保険適用外となる場合があります。
治療開始前に整骨院に労災保険の適用があるか確認し、適用外の場合は自己負担となります。
整骨院で労災申請を受ける際の注意点

整骨院で労災申請を受ける際の注意点について解説します。
整骨院の通院が長期間にわたる場合は定期的に診断書の提出が必要
| 施術内容 | 提出するタイミング | 添付が必要な資料 |
|---|---|---|
| マッサージ施術を受けた場合 | 初療診日、初療日から6ヶ月後※6ヶ月以降は3ヶ月ごと |
|
| はり・きゅう施術を受けた場合 | 初療日、初療日から6ヶ月後 |
|
| 初療日から9ヶ月以降 |
|
整骨院の通院のみでは労災保険が適用されないため注意してください。
労災指定外の整骨院を受診した場合は別途書類が必要
労災指定外の整骨院で施術を受ける場合、一時的に費用の全額立替えと「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」の提出が必要です。
領収書を添付したうえで労働基準監督署に提出し、労災保険より支払った金額の返金を受けられます。
施術を行った柔道整復師が労働基準監督署から承認を受けている場合は、被災者による立替払いは不要です。
労災保険で整骨院と病院を併用する際は事前に相談が必要
整形外科と整骨院を併用して受診する際は治療方針に影響を及ぼす場合があるため、医師からの適切な指示や許可が必要です。
整形外科での外科的な治療と整骨院での手技療法やリハビリを行う場合、連携した治療計画が必要です。
整骨院での治療で悪化した場合に責任がとれない理由から併用を禁止している病院もあります。
整骨院と病院を併用する場合は整骨院の施術が労災保険の適用外となる可能性があるため、注意してください。
整骨院で労災申請する際によくある質問
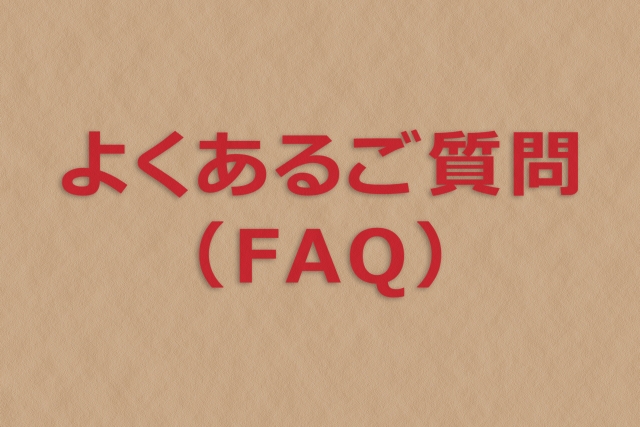
整骨院で労災申請する際によくある質問についてまとめました。
労災の診断書は整骨院でもらえますか?
労災の診断書は整骨院ではもらえません。
医師がケガの状態を確認して治療の必要性を判断し、整骨院での施術が必要とされる場合に労災申請が認められます。
また、一度労災認定されても長期間整骨院でリハビリする場合は、定期的に医師の診断書提出が求められます。
労災が適用されて整骨院で施術を受ける場合、休業補償はもらえますか?
医師から整骨院でのリハビリが必要と診断され、施術を受けるために仕事を休む場合、労災申請を行うことで休業補償給付が受けられます。
休業補償は給付基礎日額の6割、特別支給金2割を受け取れるため、治療期間中の収入減を補填できます。
労災保険と伝えずに健康保険を使用した場合どうなりますか?
労災保険と伝えずに健康保険を使用した場合、被災者が健康保険負担分の医療費を返納して、改めて労災保険に請求することになります。
受診した医療機関が医療費を健康保険に請求する前であれば返納不要ですが、場合によってはペナルティが課せられ健康保険を使えなくなる可能性があります。
労災が認められない事例と認められる事例は?
労災が認められない事例と認められる事例は、以下の通りです。
| 労災が認められない事例 | 労災保険が認められる事例 |
|---|---|
|
|
まとめ
仕事や通勤中にケガをした場合、労災保険で整骨院や接骨院を受診できます。
労災申請できる条件は、業務災害もしくは通勤災害に該当し、必要書類を提出して労災申請手続きをした場合です。
医師から整骨院での施術が必要と判断された場合に労災申請が認められるため、事故後はすぐに病院を受診しましょう。
業務災害と通勤災害によって必要な書類の様式が異なるほか、労災に対応していない整骨院もあるため、よく確認してください。
